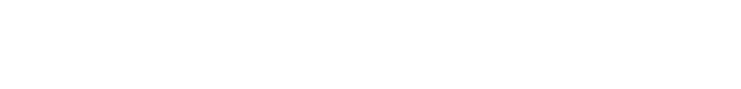森永 康平さん
(獨協医科大学 教育企画委員会 非常勤講師)
聞き手:落合隆志

内科医として臨床の現場に立ちながら、観察力や言語化能力といった診療の本質に迫る力を、どうすれば育てられるのか――。この問いに真正面から向き合い、アート作品やマンガを活用した“対話型鑑賞”の授業を構築してきたのが森永康平先生だ。
医療とアート。これまで接点が少なかったように見える領域を、教育の現場で実践的に結びつけた試みは、グラフィック・メディスンの視点から見てもきわめて示唆に富む。
本稿では、森永先生が対話型鑑賞に出会ったきっかけから、実際の授業で得られた手応え、そしてマンガの活用が拓く未来までを伺った。
対話型鑑賞とグラフィック・メディスンの交差点
「観る力」と「聴く力」を育てる:医学教育における対話型鑑賞の試み
医学教育と対話型鑑賞の出会い
- はじめに、先生が医師を目指されたきっかけについて教えてください。
-
子供の頃から『観察力が高い人』への漠然とした憧れがあったんです。何かを瞬時に見抜いたり、深く理解したりするような、そんな力を身につけたいと思っていました。例えば、一瞬とか数秒見ただけで、診断が分かってしまうとか、患者さんの心まで読み通すとか。
医師という職業には、まさにそういった能力が求められるのではないかと感じたのが、進路を選ぶひとつの動機だったかもしれません。 - スーパードクターもののマンガの主人公のような能力ですね(笑)特に影響を受けた「医療マンガ」はありますか?
-
いや、それが特にないんですよ。マンガは子供の頃から大好きでしたが、いわゆる医療マンガに強く影響を受けた経験はあまりないですね。『ブラック・ジャック』(手塚治虫 秋田書店 『週刊少年チャンピオン』連載)や『ブラック・ジャックによろしく』(佐藤秀峰 講談社 『モーニング』連載)なども、つまみ食いで読んだ感じで、特別に思い入れのある医療マンガはありません。
- 医学教育に対話型鑑賞を取り入れるきっかけについてお聞かせください。
-
実際に医学部に進み、総合診療医を目指していく中で、いざヒーローじみた能力をどう鍛えたら良いのか調べるわけです。人にきいてもインターネットを探しても、まぁ全然正解が見当たらない(笑)
名医の武勇伝的な優れた実践例の記事はたくさんあるのですが、どうやってその能力を鍛えたのか、そもそも天賦の才がありましたというようなエピソードが多く、自分のような凡人には参考になりませんでした。 - 例えば医学教育において「医師の観察力をどう育てるか」についての研修メソッドはあまり用意されていないというわけですか?
-
はい。現場では「診察がうまい」と言われる先生の観察力に感心することは多いですが、ただ、それをどう教育として共有するかとなると、具体的なトレーニング手法として明文化・体系化されているケースは極めて少ないと感じていました。
色々と模索する中で、『観察力を磨く名画読解』(エイミー・E.ハーマン(著者),岡本由香子(訳者) 早川書房)」と出会い、アートを媒介とする学びの可能性に気づきました。その流れで、京都芸術大学ACOP(エイコップ:Art Communication Project) のセミナーに参加する機会を得たのです。
ACOPは「みる・考える・話す・聴く」の4つを基本とした対話型鑑賞教育プログラムで、そこでの学びから、アートと教育、そして医療を結びつける可能性に出会ったわけです。ちなみに、そのプログラムでは、『ゆんぼくん』(西原理恵子、小学館『ビッグコミックスピリッツ』連載)というマンガを題材にしたセッションもありまして、マンガの可能性に気付いたのもこれがきっかけです。
医師には、老若男女・病状もさまざまな患者さんと適切にやり取りする力が必要になります。その中で、観察と表現をトレーニングできる仕組みとして、アート鑑賞の手法が活きてくると感じた経験でした。
具体的な実践 ‒ これまでの取り組みと成果
- 獨協医科大学で、『名画で鍛える診療のエッセンス』という講座をされています。詳しく教えてください。
-
『名画で鍛える診療のエッセンス』は宇都宮美術館および栃木県立美術館と連携して行っている授業です。
現代の医療では患者中心の診療が求められていますが、それを支えるには、単に平均的な言語力だけでなく、患者の置かれた状況に応じて柔軟に説明したり、質問したりする力が必要になります。観察力についても、診察室や病室という“一次情報”に触れる空間の中で、患者の表情やしぐさ、声のトーンなどをいかに読み取るかが重要です。
この診療に必要とされる、観察力や言語力、多様な視点の受容、コミュニケーション力を鍛えることが目的です。 - シラバスをみると、“もののあはれ”という言葉が出てきて驚きました!!
-
はい。アート鑑賞を軸とした対話型の授業を設計する上で具体的な目標設計は難しいのですが、“もののあはれ”といった日本人特有の美意識や感覚をおいてあります。
臨床現場で日々出会う、新しいひと・モノ・コトへの眼差しを重要にしてほしいという思いから”もののあはれ”を、また多数の背景や要素により複雑で流動的な現場での問題点に対して向き合い続ける姿勢として ”ネガティブ・ケイパビリティ” の獲得を学習目的として設定しています。
ちなみに、”もののあはれ”を世に広めた国文学者の本居宣長も実は日中は町医者として働いていたという話があり、後で知ってびっくりしました。
各授業の冒頭にはその日の目標を共有し、学生たちが作品に向き合う中で自らの感性や思考を深めていくプロセスを大切にしています。 - 授業で扱われるアートの種類も多様ですね。
-
題材としては一例として絵画や彫刻、ショートフィルム、マンガ、映画の予告編(『Joker』(トッド・フィリップス監督 ホアキン・フェニックス主演 2019年))などを扱ってきました。
ページや時間の軸が出現するマンガや動画は、混乱を避けるためにもカリキュラムの後半で扱うようにしています。あくまで“真相にたどり着く”ことが目的ではなく、そこから感じたことや考えたことを豊かにすることに重きを置いています。
医学部5年生を対象とした美術館に遠征しての実習では、ファシリテーターと学生を少人数のグループに分け、学生が作品を選び、それをもとに自由に語り合うという形式をとっています。実はこのスタイル、学生と一緒に“ぶっつけ本番”で作品を観ることも多くて、こちらも緊張します(笑)
こうした実践の中で、学生たちの言語化能力や、観察と解釈の区別を意識する姿勢が育っていると実感しています。”ネガティブ・ケイパビリティ”、つまり「すぐに答えを出さずに考え続ける力」も自然と身につくように思います。
マンガの対話型鑑賞への応用
- グラフィック・メディスンと対話型鑑賞には、作品を通じて気づきや共感を促すという意味で共通する部分があると考えています。題材としてのマンガについて、その特徴やお気づきの点について教えてください。
-
そうですね、絵画や彫刻に比べて、マンガは学生にとって親しみやすく、ストーリー性があるため取り組みやすいというメリットがあります。
ただ視覚情報も豊富で、登場人物の表情や場面背景など、絵画以上に多層的な読み取りが求められます。
慣れないうち、学生たちは”正解を出さななくてはいけない”という思いにとらわれがちで、発言もまばらです。そういった意味でも、慣れて実力がついてきたカリキュラムの後半に扱うことが多くなります。これまでに育んだ観察力や言語化能力を応用する格好の題材になります。
ある授業では、学生が自分の好きなマンガを持ち寄って、それをもとに対話する場をつくったことがあります。自分の“推し”を自由に語れる雰囲気が生まれて、非常に面白い時間でした。
マンガの持つ視覚表現を通じた多角的な気づきは、医療現場におけるコミュニケーション能力の育成にもつながる実感がありますね。
医学教育におけるマンガの可能性
- 現在は、医学生を対象とされている教育メソッドですが、医師の生涯教育のプログラムとしての可能性も感じます。今後、マンガはどのように医学教育に活かされていくとお考えですか?
-
さきほど診療に必要とされる力として、①観察力、②言語力、③多様な視点を受容する力、④コミュニケーション力の4つをあげましたが、それらを鍛える具体的なトレーニング手法として明文化・体系化されているケースは極めて少ないという肌感覚があります。
これらを考えると、現役の臨床医が生涯学習的に再び鍛え直す機会として活用できる可能性は十分にあると思います。
観察力や言語化力は臨床経験を積む中でも磨かれていくものですが、逆に鈍っていくフェーズも想定されます。技能が錆びないように、研ぎ直しとしての定期的な ”トレーニング” としてマンガやアートを取り入れていくセミナー形式の実践も可能性があるのかなと考えているところです。 - 海外のグラフィック・メディスン作品では、日本のマンガ作品と異なり、患者主体の視点が強調され、読者がより感情的に医療の課題を追体験できるよう設計されていることが特徴的です。この視点から、マンガの活用をどう思われますか?
-
感情の機微や関係性の描写を含む豊かな情報を、多角的に読み解く力は、まさに対話型鑑賞と通底する要素だと思います。
また、マンガは、医療現場や患者さんとのコミュニケーションにおいても、媒介として活用できる可能性があると思います。複雑な処置の流れや患者さんの心情など、文字や言葉だけでは伝わりにくい情報を、マンガという視覚的なツールで補える場面は多いと感じています。
グラフィック・メディスンの観点からも、マンガは今後ますます医学教育において活かされていくべき媒体だと感じています。
まとめ ‒ 今後の展望とメッセージ
- 先生が授業などで紹介されているお気に入りの作品について教えてください。
-
『ヨコハマ買い出し紀行』(芦奈野ひとし 講談社『月刊アフタヌーン』連載)という作品が好きで、医学教育学会でも取り上げたことがあります。ストーリーに起伏があるというよりも、「え?ここで終わるの?」という不思議な読後感があるのですが、でもどこか心地よい。読み返すたびに発見があります。「今この瞬間は二度と訪れない」という感覚を大事にしたくなる作品ですね。シラバスにある「もののあはれ」ですが、実はこの作品が発想の原点なんです。
海外の作家がこの作品から“モノノアワレ”を感じたというコラムを読んだことがあり、自分としても腑に落ちるものがありました。最近の作品でいうと『葬送のフリーレン』( 山田鐘人 (原作)、 アベツカサ (作画)小学館 『週刊少年サンデー』連載)にも同じ感覚を感じますね。
「今、この瞬間は二度と訪れない(だから顔を上げてしっかりみなければならない)」というようなメッセージは授業でも伝えていきたいと思います。 - 最後に、医学生や教育者、そしてマンガ制作者へのメッセージをお願いします。
-
マンガは、自分のペースで読めるし、たくさんの作品から“好き”を選べるというのが最大の魅力です。感動するシーン、学びのある箇所などはひとぞれぞれで、またそこに至る時間もバラバラ。
私が少し懸念するのは、教育メソッドの中でマンガの活用を語ると、「このマンガからは◯◯を感じ取らなければいけない」という尺度が、観劇体験を窮屈にし、”好き”から遠ざけてしまうのではないかということです。
誰かが「この作品からこれを学ばなきゃいけない」と決めるものではありません。
マンガは自由にのびのび読めてこそ、好きを大事にすることで、また読もう、という何より価値のある未来につながっていくのではないかと思います。“他人の目や一般的な尺度・建前を気にしすぎて好きなもの、こと、自分の感覚が腐っていかないように”