小森康永さん
精神科医

今回の「GMな人びと」は、精神科医で臨床心理士の小森康永(こもり やすなが)さんです。
小森さんは、『グラフィック・メディスン・マニフェスト』(北大路書房、2019年)の翻訳者であり、
ブライアン・フィース『母のがん』(ちとせプレス、2018年)の解説も担当されています。
- 簡単に自己紹介をお願いします。普段はどんなお仕事をなさっているのでしょう?
- 精神科医です。現在、愛知県がんセンター 精神腫瘍科部長をしています。
私は日頃からマンガを読む人間ではないし、医学教育を生業にしているわけでもないので、グラフィック・メディスン(GM)の紹介などする立場にはないわけですが、なぜかその『グラフィック・メディスン・マニフェスト』を一冊、仲間で訳してしまいました。何か新しいことに目が向くのは決まって患者さんからの刺激によります。 - 以前から患者さんとのやりとりの中で、マンガが登場する場面はあったのでしょうか?
- 『グラフィック・メディスン・マニフェスト』を翻訳するきっかけもそうだったわけですが、それ以前にも臨床にマンガが登場する場面はいくつかありました。
岐阜大学で小児科の研修医をしていた頃、時折入院してくる喘息の中学男子を、主治医は「ペアレンテクトミー※1だよ」と(本気かしゃれかもつかぬ素振りで)、心身症に興味のあった私に決まって担当させました。
ちょうど雪が積もった朝で、いつもなら病院から登校しているはずの彼がまだ病室に残っていて、珍しく教授回診を受けることになりました。そこで彼が突然、模造紙いっぱいに描いたマンガをベッドサイドで供覧したんです。それは大名行列に仕立てた教授回診風景でした。これが笑えないのは、大名がチョンマゲに着物(で教授の頭部と白衣姿が似ている)からです。監督不行き届きでまたお目玉かと思ったのですが、教授は満更でもない顔をして「なかなかうまいな」とだけ言いました。これは、ある意味、マンガの力を初めて実感した時だったのだと思いますね。数年後、心身症外来を開くと、不登校の 子どもの中にマンガ闘病記を描いて持ってくる子どもたちがいたので、“Drawing success story”などと呼んで治療に役立てたものです。
マンガに限らず描画療法は家族画※2もスクイグルゲーム※3も守備範囲でしたし、精神科医になってからは統合失調症の家族向けに外在化人形劇※4も始めました。擬人化された統合失調症「ミスター・スキゾ」が登場する寸劇「ミスター・スキゾ完全独占インタビュー」は、留学仲間でウィーンのシュテファン・ガイアホッファーのチームが気に入ってくれて、5本のとても素晴らしい心理教育DVDに展開したのが自慢です(http://www.ist.or.at)。※1 ペアレンテクトミー(parentectomy):両親離断療法。peshkinにより提唱された小児喘息の治療法で、peshkinは家庭内のアレルゲンと両親との心理的葛藤からの離断が奏効するとしている。
※2 家族画:心理面接の手法。家族の様子を描くことで、描き手と家族の関係や、家族内の人間関係を読み解く。
※3 スクイグルゲーム:イギリスの伝承的な絵描き遊びをWinnicottが精神分析療法へと発展させたもの。治療者と患者の一方が描いた自由ななぐり描きの線を、他方が加筆して1つの絵に仕上げる。
※4 外在化人形劇:統合失調症(Schizophrenia) を擬人化することで外在化した人形劇。
- 小森さんとグラフィック・メディスンとの出会いについて教えてください。
- 2006年にがんセンターに移ってから、がんの家族教室をどこよりも早く始めたわけですが、がんの家族教室を続けるにあたり、がん教育の副読本を探し、ブライアン・フィースの圧倒的な『母のがん』を見つけました。そして、出版時にその本の解説を書こうとしたときに、「グラフィック・メディスン」を発見したわけです。ナラティブ・メディスン(NM)には結構入れ込んでいたので、はじめ冗談かと思いましたが、これまた驚愕せざるを得ないものでした。あまりに真剣なのです。以前からマンガと医学はかけ合わせたら面白いのではないかとは思っていました。この喩えに注意して欲しいのは、どちらかが水準以下だったら(喩えを続けるなら、1以下であれば)結果は寂しいものになるということです。そこが足し算とは違う。GMな人びとはもちろん重々承知のことでしょう。
NMが当初、「ナラティブとエビデンスは医療の両輪である」というプロパガンダで紹介された時は、耳を疑ったものです。私自身は、喩えを使うなら、ナラティブはクジラで、エビデンスはイルカだと思っています。どちらもクジラ目であり、違いはサイズでしかない。イルカは小利口で愛らしいかもしれないが、『白鯨』やミシュレの『海』に書かれたほどのクジラの神聖さはない。それはさておき、マンガと医学の関係を文学的な喩えで続けるなら、GM(という名詞)を実践するところを想像するよりも、「医学をマンガでひらく」(という副詞的)イメージの方が適切なのではないかと思います。こんなところに私は惹かれますね。 - 小森さんは臨床でGMをどのように実践されているのでしょうか?
- 私自身がどのようなGM実践をしているか、NM流に、<読む>、<描く>、<描いたものを共有する>という視点で、順に紹介していきましょう。
読むことで言えば、『母のがん』を使った「マンガでわかるがんサバイバル」講義があります。例えば、母の泣き顔が前面に広がる94ページをスライドに映し出して、「トータルペイン」がなぜ分割されてはならないのかを説明する時、私は他では決して得られない手応えを感じます。それは、マンガ以外では実現できないのではないかとさえ思います。このコマは、実は、ものすごく興味深いのです。ヒントは、このコマが全112ページ中の94ページだということです。つまり、ここでの対話は、(脱毛が示すように)化学療法が終わった時点でなされているのです。母の発言「5%ですって?!」は、普通、診断時に自身のがんのステージを教えられ、5年生存率を自分で調べて(あるいは誰かに知らされて)すぐの自問であるべきなのです。それを聞かされる長女にしてみれば、「今更、それはないでしょう」という反応。そんないい加減な認識でこれまでどうやって頑張ってこられたの、ってところ。一方、患者さんご本人にしてみれば、5%だってことを忘れていたから(あるいは否認できたから)、ここまで(もっと高い確率だと信じて)治療を続けてこられた、ってところかもしれません。何かに基づいて、治療に希望を託すということが、いかにあやふやなものに基づいているかが明確になる対話です。そして、そもそも希望とは何かということについても考えさせられます。こんなに込み入ったやりとりが、たった1コマで表現されるなんて、やはりマンガはすごいと思いますね。そして、これがこのコマの肝であることは、どうやったらわかるのかという話になります。それは、このコマを5W1Hで表現してみたらわかるのです。ナラティブですね。時間の表記がそこに入ることで、この対話が奇妙なものであることが判明し、治療というものの深みを考えることができるわけです。マンガはわかりやすくていいよね、なんて能天気な考えは捨てた方がいい。ちなみに、この講義は愛知県がんセンター緩和ケアセンターの家族教室の第1回講義の定番となっています。
ちなみに、ステージ分類が「空間分類」であって「時間分類」ではないことは99%の患者さんが理解していません。医者も全く説明しない。だから、がん細胞が一つできてから死ぬまでを4つに分けたのがステージ分類だと思っていらっしゃる。それだとステージⅣは死の一つ前ということにしかならない。あるいは「再発転移したから私はステージⅣで、もうアウト」なんて話にもなる。ステージ分類は初発診断時にしか使いません。ですから、いくら空間的に広がっていたとしても(手術ができなくても)薬が有効なら、がんは消えるのです。奇跡でもなんでもありません。そんな薬を開発した製薬会社は素晴らしい。小森さんの「マンガでわかるがんサバイバル」の取り組みは、愛知県がんセンターのHPでも詳しく紹介されています。ぜひこちらもご参照ください。
https://www.pref.aichi.jp/cancer-center/hosp/15anti_cancer/special/10.html - 愛知県がんセンターでは『母のがん』を課題図書にした読書感想文コンクールを企画されていますね。それはどういった取り組みですか?
- 2019年にスタートした新しいがん教育の試みです。若者が読書によりがんサバイバーについて学ぶと同時に、がんについて⾃主的に学ぶきっかけとなることを⽬指して企画したもので、中高生対象で始めましたが、翌年からは一般も参加できるようにしました。
『母のがん』のお気に入りのページを1つだけ選んで、作者は何を考えているのか、なぜ自分はそれを選んだか、そこで何を発見したのかをA4 1枚に800字以内で書くだけです。
患者さんの中には「『母のがん』は私のバイブルです」と言う人もいます。自分の闘病体験を比較参照することで静かな対話がいつでももてるというのです。がんサバイバルという旅のしおりのように使われているようです。 - <描く>、<描いたものを共有する>に関して、どのような取り組みをされていますか?
- マンガを描くワークショップは、2018年8月、日本家族療法学会ワークショップで初めて試みてみました。そこでは、団士郎さんと安達映子さんの3人が講師を務めました。さきほどお話した『母のがん』の94ページを1コマ目にして4コママンガを描いてもらったのです。説明は「がん患者が5年生存率について知らされたところです」とだけ提示しました。その代表作、岡本潤子さん(帝京大学文学部心理学科)の作品を紹介しましょう。
作者であるブライアン・フィースとMK・サーウィックに、このワークショップについて伝え、参加者の作品も7枚添付したところ、すぐにこんな返信がありました。
ブライアンからは「気をつけた方がいいよ、君はとても危ないところに差し掛かっている! 2010年、私の友人イアン・ウィリアムズはロンドンでGMのワンデイ・ワークショップを開催したせいで、今や彼の人生はGMによって完全に乗っ取られてしまったんだよ!君たちのワークもいけてるようだね。参加者はワークにやって来たとき、自分たちが何を期待されているかわかってなかったと思うよ。君たちの熱意が彼らを動かしたんだと確信しています。『母のがん』のページに触発された参加者の漫画を見せてくれてありがとう。私よりもずっといいアイデアもあるね。文字は読めなくても、絵がとてもよく物語を伝えてくれます。これは、言語や文化を超えたマンガの大きな力の一部だよ」
そしてMKからはこんなコメントが同日に到着しました。
「ヤス、ブライアンの言う通りね。私は今、GM年次大会から帰ってきたところ。英語圏以外の国にもミッションを拡大するのが私たちの目標です。スペイン語を話す国の同僚たちは、Graphic Medicine in Spanishの「姉妹サイト」(https://medicinagrafica.com/)を作ってくれました。私が興味のある日本の同僚たちとあなたを結びつけて、あなたが知っている人たちを集めたら、それは何か興味深いものになるんじゃない?残念ながら、ギャラは出ません。今のところ、これは私たち全員の愛の労作なのです」
そして、これをシェアした岡本さんからはこんな返信が。
「ブライアンさんとMKさんからのお返事をシェアしてくださり、ありがとうございます。ウィットとエネルギーと温かさに満ちたお返事。こういうお仲間があるということは素晴らしいですね。雑事に追われる日々を過ごしている私でございますが、このたびのWSでは、久々のクリエイティブな作業をしただけでなく、色々な示唆をいただき、ちょっと新しい気持ちになっています。こういうことが、学会に出向く良さだなぁと改めて思っています」。以上、こんな形の対話というものが、当日、描いたものを共有する中で生まれた雰囲気だと想像していただければ、間違いありません。
- 今後のグラフィック・メディスン協会の活動に一言いただけますでしょうか?
- GMの学会には行ったことがなくHPで拝見するだけですが、大変アットホームな良い集まりであることは確実ですね。途方もなくエネルギッシュだとも感じます。どこまで伸びるか興味津々。私自身、マンガのことを職場などで口にするようになってひとつ気づいたのは、意外にマンガを描く人がいるということでした。
だから日本でも、結構期待できるのではないかなぁ。ただ、そこに医療人文学の人たちがどのくらいコミットしてくれるかが成否の鍵だと思います。それがないと、医学をマンガでわかりやすく解説するだけの話になりかねないから。NMが「患者さんのお話は傾聴しましょうね」という話に終わりかねないように。
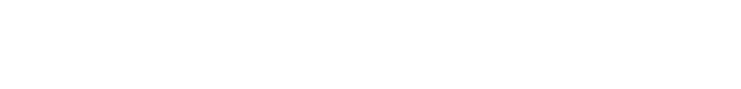


の作品.jpg)