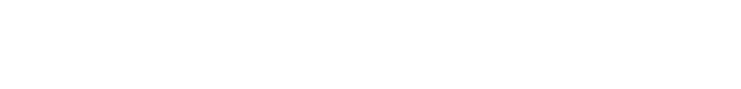法医学の天才が声なき遺体から真実を暴く連作ミステリー

- キーワード
- 法医学
- 作者
- 杜野亜希
- 作品
- 『屍活師 女王の法医学』
- 初出
- 『BE・LOVE』(講談社、2010年3号-2018年18号)
- 単行本
- 『屍活師 女王の法医学』(講談社、BE LOVE KC、全18巻、2010年-2018年)
※「初出」は単行本のクレジットに基づいています。
作品概要
国立H大学医学部4年の犬飼一(はじめ)は臨床医の外科希望だったが、法医学研究室に実習配属される。そこには、美人だが、ガサツで上から目線の准教授・桐山ユキがいた。自分を「ワンコ」と呼んで人間扱いしない「女王」然としたユキと、同級生たちにも「どんなに情熱あっても生きた人を助けることにはならない」と思われている法医学そのものへの反発から、一の実習は嫌々始まる。
ある時、事件を疑われる遺体の解剖に立ち会った一は、ユキがそこから次々と紡ぐ情報を受け取ることで、死体から立ち現れた生前の姿を、一瞬の映像として「視る」。同じように、その「遺体の思い 死の瞬間の姿」を映像として視ることのできるユキは、「屍(しかばね)は活(い)ける師なり」と言い、隠されていた死の原因、生前の死者の思いを明らかにしていくのだった。
法医学の天才が、声なき遺体から真実を暴いていく連作ミステリー。2013年には、松下奈緒主演でテレビドラマ化された。
「医療マンガ」としての観点
感情を入り込ませて検死を行おうとする一に対し、ユキは、「ただ遺体のあるがままを見なさい/あんたの思い入れはこの人の真実と関係ない」と諭す。もの言わぬ死体が相手だからこそ、客観的な事実を積み上げて真実にたどり着くしかない、という発想は、ロジカルな本格ミステリーというジャンルと相性がいいように思える。実際、監察医務院に勤務していた法医学者・上野正彦によるノンフィクション『死体は語る』(1989年)は、ミステリー小説さながらに読まれ、大ベストセラーとなった。しかしながら、木村直・画/香川まさひと・作/佐藤喜宣・監修『監察医 朝顔』(2006-2013年)や古賀慶『トレース 科捜研法医研究員の追想』(2016年-)のようにテレビドラマ化したものもあるものの、法医学ミステリーマンガというのは案外多くない。英米圏のように捜査権も持った監察医や検死官が、職種として存在しないからかもしれない。
ところで、単行本第1巻の「あとがきマンガ」によると、本作を描くことになるきっかけは、元々製薬会社のOLである作者が、本作の舞台のモデルでもあるH大学薬学部時代に受けた法医学関連の授業にあるそうだ。担当教授が、授業で使っている骨格標本を「この方とは生前お友達だった」と紹介し、まるで死者と「いまも話をしているような」雰囲気だったことが印象に残っていたのだ。『屍活師』はもちろんフィクションだが、そこで表現される、法医学現場における「死(体)との距離感」はリアルなものだったのである。