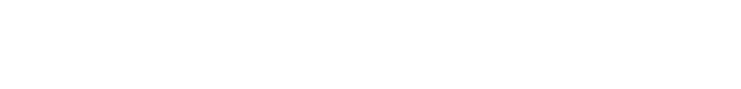児童精神科を舞台に、発達障害のある子どもや家族、当事者の生きづらさを描く

- キーワード
- 児童精神科発達障害虐待
- 作者
- 漫画:ヨンチャン
原作:竹村優作 - 作品
- 『リエゾン -こどものこころ診療所-』
- 初出
- 『モーニング』(講談社、2020年第14号-)
- 単行本
- 『リエゾン -こどものこころ診療所-』(講談社、モーニングKC、既刊2巻、2020年-)
※「初出」は単行本のクレジットに基づいています。
作品概要
子どもの頃に出会った小児科の先生に憧れて、自らも小児科医を目指す大学病院研修医の遠野志保。志保は病院に入院している子どもたちに懐かれる親しみ易いキャラクターを持ついっぽう、遅刻や忘れ物、早とちりのミスなどの常習犯で、研修先の大学病院では「問題児」扱いをされている。ある時、志保は研修中に彼女は患者の命に関わりかねないミスを犯してしまい、大学病院の教授から、小児科医になるのを諦めろ、とまで言われてしまう。その後、大学病院を実質的に追い出された志保の次の臨床研修先は、地方の小さな児童精神科の診療所「佐山クリニック」であった。志保はそのクリニックの院長・佐山に初対面で、志保の歯止めの効かないドジでおっちょこちょいな行動は性格の問題ではなく、個性でもなく、発達の凸凹と呼ばれるものと説明を受ける。そして「あなたは発達障害です。」と佐山に言われる。最初は驚きショックを受ける志保だが、佐山と共にクリニックを訪れるさまざまな発達障害や様々な精神疾患のある子どもたち、その家族、そしてその周囲にいる支援者や教員たちと関わり合いながら、自分自身の凸凹とも向き合い成長をしていく。
「医療マンガ」としての観点
本作品は、児童精神科医療の世界を舞台に、発達障害のある子どもとその家族(親)への臨床の様子と親子が変化していく過程の物語と主人公である発達障害当事者&研修医の志保の成長の物語という2つの柱がある。1つの柱である診療現場の物語は、(天才肌の精神科医が活躍するものではなく)医師と心理士や看護師などのスタッフたちが共に家族に寄り添いつつ、医療者としてできることをチームで模索していくプロセスを丁寧に描いている(なお、本作品の題名である「リエゾン」は、「連携」「連絡」を意味するフランス語で、医療の分野ではチーム医療・連携のことを指す)。物語の中で学校の教師たちとのケース会議や看護師による訪問看護についても詳しく描写されているのは、精神科医療が診療室という場でのみ行われるものではないことを伝えるためだろう。また本作品で語られるエピソードには、子どもや家族が劇的に良くなったり、抱えていた問題が解決して一件落着、という描写はない。「僕たちにできることは」あくまでも「少しずつ…」子どもと親の間の「関係を取り戻す手助けをし続けるしかないんです」という、児童精神科医の佐山の台詞にもそれがあらわれている。解決策や支援の方略より、診療や相談などの場面での、子どもや親たちの話す何気ない言葉や表情や目線やしぐさのリアルさが作品で強調されているのは、医療漫画だからこそ伝えられるポイントではないかと思う。
もう1つの柱である研修医・志保の成長物語は、自分が発達障害であることを告げられた志保が(なお、それを志保に告げた佐山自身も発達障害の当事者である)、戸惑いながらも、佐山による診察(知能検査の結果のフィードバックなど)や、診察室を訪れる子どもたちとのやり取りから、自分自身の苦手・得意を知り、どう足りない部分を補い、自分に合ったオリジナルなやり方で活躍できるかを模索していくものだ。2巻に掲載されたカミングアウトの回は、志保とその友人たちとのやり取りを通じて、発達障害当事者の「普通ではくくれない大変さ」を周囲にどう伝えていけば良いのか、という問題にも焦点が当てられている。なお、もう一人の「発達障害当事者の精神科医」である佐山の作品内の描写は、当事者の視点を活かした診療のコメントなどは出てくるが、発達障害を背景にした優れた能力などがある訳ではなく、子ども目線を大事にした、少々変わったところのある医者、という感じだ。この佐山の存在も、発達障害を特別な能力でも欠陥でもない「凸凹」と表現する本作品のスタンスをよく表していると考える。