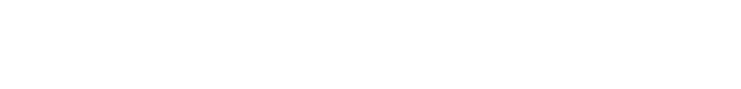もし家族が大病したら?
――「セミフィクション」による「第二の患者」としての家族をめぐる物語

- キーワード
- セミフィクション介護家族(「第二の患者」)若年性認知症
- 作者
- 吉田いらこ
- 作品
- 『夫がわたしを忘れる日まで』
- 初出
- X(旧Twitter)「若年性認知症の父親と私」
- 単行本
- 『夫がわたしを忘れる日まで』(KADOKAWA、2023 年)
※「初出」は単行本のクレジットに基づいています。
作品概要
夫・翔太45 歳、妻・彩43 歳、小学5年生の息子・陽翔は家族3人で幸せに暮らしていたが、夫の物忘れが少しずつ見過ごせないものになっていく。病院にて若年性認知症と診断されて以降、家族のあり方は変容を余儀なくされる。妻の視点から、優しい人柄であった夫が「別人」のように変化していく様子、家計・子育てを含めて家族のあり方を大きく変容させざるをえない不安や覚悟、夫の闘病に寄り添う心理的・身体的負担が描かれる。夫はやがて献身的に寄り添う妻の存在すら認識できなくなってしまうかもしれない。
「生きてるのに死んじゃったみたいだ。そして私の心ももうなくなりかけている」。時間や場所の感覚が失われていき、やがては家族の顔すら認識できなくなるかもしれない。「第二の患者」とも呼ばれる家族の視点から、家族の病気によってそれまでの生活のあり方が激変する3年間におよぶ日々が日常のエピソードを通して描かれる。
「医療マンガ」としての観点
「あとがき」にて、作者が高校生の頃、当時40 歳の父親が、病気の後遺症で脳に障害を負い家族を認識できなくなった背景について触れられている。本作に先行して、作者はSNS 上で「若年性認知症の父親と私」というエッセイマンガを発表している。その際に描かれた、若年性認知症の父親をめぐる作者自身の体験や気持ちが、「セミフィクション」としての本作では、同じ病を患う男性とその家族にまつわる妻視点の物語に継承され、昇華されている。
作者自身が高校生であった時には、父親が突然、別人のように変容してしまう状況をうまく受けとめきれず、母親に対応をすべて任せてしまった「後ろめたさ」を長く抱えていたという。その点で本作は、「もしあの時こうすることができていたら」「あの時家族はこういう想いを抱えていたかもしれない」を、フィクションを交えて、娘ではなく妻の立場から追体験する試みにもなっている。その点で、自伝的要素を踏まえて、「第二の患者」として家族の病気に向き合った高校生当時の想いや体験をマンガで表現するグラフィック・メディスンの実践になっており、「セミフィクション」の枠組みを通して普遍的な物語としての奥行きを示す効果をあげている。
働き盛りである夫の介護に、子どもの中学受験の準備も重なり、主人公の彩は将来に対する不安、現在の生活の負担に押しつぶされそうになっていく。夫の若年性認知症を周囲に相談することもできず苦難の日々が続く。本作においては、夫の両親がサポートしてくれる体制が整い、主人公の彩の職場でも彩の心に寄り添ってくれる同僚の存在が救いとなる。病気を抱えた家族を支える「第二の患者」の視点から、変容を余儀なくされる日々の戸惑いが丁寧に綴られている。