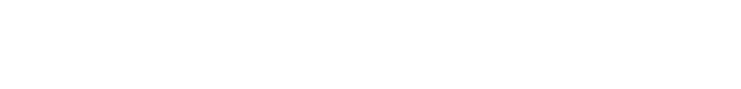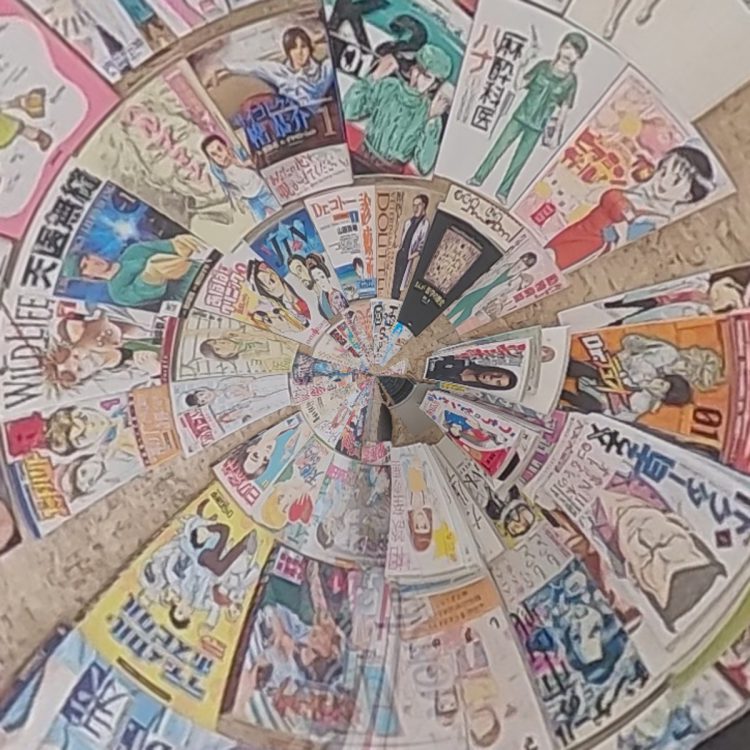一般社団法人日本グラフィック・メディスン協会代表挨拶に代えて
一般社団法人日本グラフィック・メディスン協会は、我が国の医療領域(現場・教育・研究)にコミックス/マンガおよびその他のヴィジュアル表現を導入し、日本の医療をわかりやすく一般に開き、医療の発展に寄与することを目的に2018年に設立されました。
2007年にイギリスで産声をあげた「グラフィック・メディスン」は、医学、病い、障がい、ケア(提供する側および提供される側)をめぐる包括的な概念であり、数量化による捉え方(一般化)が進む中でこぼれ落ちてしまいかねない「個」のあり方に目を向け、臨床の現場からグラフィック・アートまでを繋ぐ交流の場を作り上げようとする取り組みです。その一環として、マンガをコミュニケーションのツールとして積極的に取り上げたり、当事者自身がマンガの制作を通して気持ちや問題を共有したりする活動が展開されています。
グラフィック・メディスンが英語圏で発展してきた背景として、移民社会などの多様性を挙げることができます。ただ、これは多言語多文化でのコミュニケーション不全をグラフィカルにわかりやすくするといった単純なものではありません。
洋の東西を問わず、医師と患者の医療情報は非対称なものであり、双方の対話への努力なくして意志を伝達しあうことは困難を伴います。
医療分野とマンガを接続することで、マンガを通した「語り」は、医療従事者・患者相互に対し、高度化する医療状況や患者・家族の当事者経験をわかりやすく伝達し、理解することを助けます。そして、グラフィック・メディスンはそこからさらに、その背景にある人や出来事、経験などの多義性を拓いていくことを目的としています。
医療従事者と患者間の円滑なコミュニケーションを目指し、医療従事者向けの教育現場でマンガを通して患者の視点を体験するワークショップなどの取り組みも積極的に行われており、この動きは、2019年の日本家族療法学会において「医学教育と患者ケアにマンガを使おう!―グラフィック・メディスンのすすめ―」と題したシンポジウムが開催されるなど、高齢化、多様化が進む日本社会においても期待される領域となっています。
英語圏で誕生したグラフィック・メディスンの概念を日本において発展的に導入する上で、わが国の豊潤なマンガ文化をどのように有効に活用しうるかが鍵となります。
当協会では、世界的なグラフィック・メディスンの動向を参照しながら、医療をめぐる日本のマンガのジャンル文化についても探求していきます。
「医療マンガ」と一口にいっても、「ストーリーマンガ」における個々の作品での医療の扱い方もさまざまであり、「エッセイマンガ」の領域もまた、患者、家族、医療従事者の視点による体験記から、取材にもとづいたノンフィクションとしての作品まで多岐にわたります。四コマを軸にした病院を舞台にするギャグマンガもあれば、啓発的な目的を持つ「解説マンガ」の系譜もあり、マンガを医療現場で応用する取り組みも示されています。
さらに広義の医療をめぐるマンガの応用例として、障がいのある人たちに向けた「LLマンガ」の取り組み、精神疾患などの特定の症例を扱った作品、医療従事者の視点による回想録(グラフィック・メモワール)、複数の視点や証言を織り交ぜたドキュメンタリーの手法を導入した作品の傾向などもあります。
日本の医療マンガ作品には、医療従事者の置かれている状況(一例として、過剰労働などの構造的な問題など)および患者が抱えている不安や医療に対する期待、新しい医療制度に対し想定される状況の変化などを幅広い層に伝える機能もあり、医学教育への応用とも異なる観点からの社会的評価も有効でしょう。
2020年は手塚治虫が『ブラック・ジャック』に先駆けて発表した医療マンガ『きりひと讃歌』を発表してからちょうど50年目にあたります。
我が国の65歳以上人口は総人口の28.4%にあたる3,589万人に達していますが、ここに医療問題と高齢化とマンガという横串を指すと、実は、この世代が手塚治虫をはじめとするマンガ文化の中で育った世代でもあることに気づきます。我が国が抱える医療のさまざまな課題を、世代を超えて解決していく上で、マンガが有益な共通のツールとなりうることでしょう。
当協会はマンガ表現がどのように医療の領域を扱うことができるかを包括的に探る試みとして、医療人文学とも連携し、医療従事者と人文系研究者、表現者とを繋ぐ交流活動の場を提供することを目指しています。
多くの皆さんとご一緒にその可能性を探っていくことができますことを願っています。
2020年9月 協会代表 中垣 恒太郎