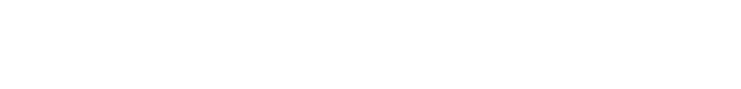中垣 恒太郎
「老・介護・認知症」―「老い」にどう向き合うか?
人は誰しも老いる。しかしながら、本人の老化、あるいは、家族の介護など身近な問題となるまでは、その当たり前のことに気づきにくいものであろう。マンガ表現によって、老いや介護の世界をどのように描くことができるのであろうか。
介護の現場における問題をとりあげた先駆作となった『ヘルプマン!』(くさか里樹、『イブニング』連載、講談社、2003~2014年)、『ヘルプマン!!』(『週刊朝日』連載、朝日新聞出版、2015~2017年)は、猪突猛進型の主人公の青年が特別養護老人ホームにて老人介護に奮闘する物語であり、凄惨なまでに厳しい介護の状況、介護虐待の現実、保険制度や介護職員の待遇など、複雑に絡みあう現場の問題を広く知らしめるのに貢献した。綿密な取材に基づき現場に通暁した上で、介護者、家族、本人などさまざまな視点から老人介護をめぐる状況を捉えた野心作であり、10年を越える長期シリーズとなった。
21世紀以降、主としてエッセイマンガの分野で、医療従事者・介護者の視点、家族の視点、そして当事者の視点などから「老い」や「障がい」を捉える作品が目立った動きを示している。本書のレビューでとりあげることができなかった作品をいくつか参照してみよう。
家族の視点からの物語として、ニコ・ニコルソン『わたしのお婆ちゃん 認知症の祖母との暮らし』(講談社、2018年)は、アルツハイマー型認知症を患う祖母(「婆ル」)の「奇行」に翻弄される家族をおばあちゃん子として育った孫の視点から描く物語である。身近な存在だったはずの祖母が変容し、それに伴い家族の関係性もぎくしゃくしていく過程の戸惑いや葛藤が丹念に綴られている。祖母に対し愛情を抱いている孫娘としての筆者が結局は、祖母の存在を受けとめきれなくなってしまい施設に委ねる決断を下すに至る。「あの時どうしていればよかったのか?」。正解は一つではないし、そもそもどのような選択をしたとしても何らかの後悔は残ってしまうものかもしれない。この作品を制作する過程自体が、認知症を患って以降、祖母が見ていた世界を筆者が追体験する試みにもなっている。
「心の病気」とどう向き合うか?
心の病気もまた当事者以外にはその症例が実際にはどのようなものであるのか、わかりにくい領域であろう。マンガによる表現を通して、それぞれの症例を抱える人たちの視点からどのように世界が認識されているのかを垣間見ることができる。
木村きこり『統合失調症日記』(ぶんか社、2018・2020年)はタイトルにあるように、「統合失調症」を発症した高校時代の回想から、幻聴や幻視に囲まれた日常が描かれる。「あとがき」によれば、「治療の一環としてドクターに口下手な私が日々あったことを伝えるために始めた」とあり、まさしくグラフィック・メディスンの実践となっている。
Tokin『実録 解離性障害のちぐはぐな日々― 私の中のたくさんのワタシ』(合同出版、2018年)は、自分が自分であるという感覚が失われている状態を指す「解離性障害」をめぐる自伝的エッセイマンガである。「はじめに」にある説明によれば、「抱えきれないようなストレスやつらい出来事に遭遇してしまった時」、「つらくなったら自分と感情を切り離して」しまうことにより、「切り離された感情が徐々に別の人格を形成してしまう」症例が「解離性障害」であるという。加えて、躁うつ病として知られる「双極性障害」を併発していた筆者は、まず自分が抱えている違和感が何に起因しているかがわからずに戸惑っている。「私と世界との間には とても大きな川があって みんなはその川の向こう岸にいるような気がする」が、「でも私はなぜか そちら側には行けない」。心も体も一見、病気ではないために、高校時代の筆者が親に精神科に行きたいと申し出て精神科クリニックに通うも解決の糸口は得られない。「求められるのは『患者力』?!違和感を説明するのは難しい」という章題に付されているように、そもそも自分の症例がどのようなものであるのかを見極めること自体が難しく、その症例について説明することはさらに難しい。
マンガによってやわらかく表現されているものの、突然の退職後の入院生活、自殺未遂や死にたいという気持ちが随所に盛り込まれ、実際には苦闘に満ちた半生であったことが窺われる。「あとがき」においても、「今まさに、死にたさや苦しさを抱えている方」、「そういった苦しさを抱えた方の近くにいらっしゃるご家族やご友人の方」にメッセージが向けられている。
作品全体を通して、「普通」や「まとも」の概念が揺らいでいくのではないか。解離性同一性障害は確かに珍しい症例であるかもしれないが、その視点から「普通」とされる世界がどのように映っているかを疑似体験する機会を得ることで、それがいかに「普通」という概念に抑圧されているかをあらためて考えさせられる。
モンズースー『発達障害と一緒に大人になった私たち』(竹書房、2020年)は、筆者自身もADHDの当事者であり、発達障害の疑いがある息子を持つ立場から、「発達障害」とみなされていた人がどのように大人になっていったのかをめぐる取材に基づいたエピソードの集積である。筆者自身を含む9つの例からは、それぞれの苦労のあり方もさまざまであり、人生の多様性をあらためて一望できる。他の症例と比しても、「発達障害」は近年、周囲の理解が進みつつあるが、その一方で情報の偏りもあり、発達障害やアスペルガーという言葉が差別的に使われる向きも少なくない。なんとなく知っているような気がしていても、「発達障害」の当事者が年齢を重ねていく様子などは、よほど近い存在がいない限りは関知していないのが現実ではないか。
老いや障がい、精神疾患は誰にとっても他人事ではなく、突然に身近に起こりうるものだ。マンガ表現を通して、今ある世界を別の角度から見る視座を得ることにより、私たちがつい「当たり前」と思い込んでしまっている価値観について立ち止まって考えてみることができる。