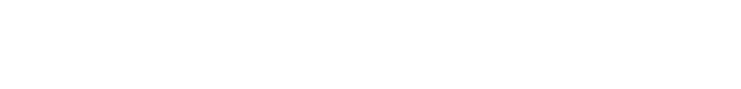表 智之
「医療マンガ」黎明期の1963年、青年医師を主人公とする不思議な味わいのマンガ作品が少年マンガ誌に登場したが、残念ながら短命な連載に終わった。ちばてつや「ハチのす大将」(『週刊少年マガジン』1963年1月1日号~5月19日号)である。北米のテレビドラマ「ベン・ケーシー」が前年から日本でも放送され大ブームとなり、年初早々から複数のマンガ誌に登場した医者ものの中の一本で(注1)、短期連載で終わった理由は、ちば本人が各所で繰り返し語っている(注2)。
ちばの弁によれば、作中の医療描写の不正確さを具体的に指摘し、たしなめる手紙が、先輩格の漫画家・つのだじろうより届き(しかも「巻紙」に毛筆で!)、恥じ入って慌てて連載を止めたのだと言う。面白過ぎる話でやや脚色がありそうだが、作品を見ると頷ける部分もある。
主人公・嵐大介は総合病院に勤める外科医で、品行方正とは言い難いが情に厚く、港湾労働者の住まう貧困地帯「ハチのす町」で彼の父親が営む診療所[図1]をかけもちで手伝い、町の子供たちからは「大将」と慕われている[図2]。「ベン・ケーシー」に加えて、山本周五郎『赤ひげ診療譚』(1959年発表され、1960年にテレビドラマ化)の影響も見て取れよう。
外科医の大介がコレラについて論文を書くなど、なるほど「医療」描写は正確ではないし、中盤、ハチのす町支援のために賞金を稼ごうとバイクレースに大介が出場するなど、作品の方向性を手探りで進めた形跡もある。その一方で、のちの『あしたのジョー』(原作・高森朝雄)にも通ずる「貧しさ」への温かなまなざしは、ちばならではの魅力である。
注目すべきは、貧困ゆえに医療から遠い人々の存在にしっかりと焦点が合わされている点で、これは「赤ひげ」の影響とばかりも言えない。なんとなればこれ以前、1950~1960年代のマンガにおいては、貧困と病苦の強固な結びつきが繰り返し描かれたからである。
例えば、白土三平の初期作品『消え行く少女』(貸本/日本漫画社、1959年)。幼少期に広島で被曝し、いわゆる「原爆症」を患った少女を主人公とする異色作だが、この時期の少女向け貸本マンガには“難病少女もの”とも言うべき人気ジャンルがあり、その潮流の中で描かれたものと目される(注3)。[図3]は物語の冒頭、狭いあばら家でボロ布団をかぶる病人の枕元へ往診の医師が訪れるという、貧困=病苦の定型表現である。
貸本マンガとは、書店ではなくレンタル専門の「貸本屋」へ卸すことを目的に出版されたマンガ雑誌・単行本である。隆盛期は1950年代後半から1960年代前半で、貸本屋が多い時で全国に3万軒程度と言われていたから、中小零細の版元による、書店流通よりは小規模な商いである。その分小回りも利いて、世間の流行を貪欲に取り入れていた。
吉備能人の概括によれば(注4)、少女向け貸本マンガでは“母子もの”と呼ばれる、紅涙しぼるがごとき切々たる悲劇が人気で、主人公の少女の母は、消息不明か事故死か闘病中であり、とりわけ結核を患っていることが多かったという。劣悪な環境での過酷な労働と栄養失調により罹患し慢性化することから「貧困」と直結した病苦である結核。貸本マンガのそのような傾向は、戦後日本社会の偽りなき実相であったろう。復興が進み、結核の罹患者が現実社会で減少すると、入れ替わりに「原爆症」が多くみられるようになっていく。また、1960年代の初頭には、『愛と死をみつめて』(河野實・大島みち子の往復書簡集が1963年刊行され、翌年からテレビドラマや映画などで大ブーム)の影響下で、行き届いた医療の下での若く美しく清らかな死のイメージが隆盛となり、貧困は後景化していったという。
高度経済成長により、生活水準が全体として向上したのみならず、世界に誇るべき日本の「国民皆保険制度」が全市町村で成立したのが1961年4月。医療は国民が等しく享受すべき社会保障となり、白土が描いたような医療から疎外された貧しい暮らしは過去のものとなった――少なくとも建前としては。この時期に大ヒットするテレビ番組「シャボン玉ホリデー」(第1期・1961~1972年)で、[図3]のような“あばら家で病臥する貧者”の定型表現は、小奇麗に換骨奪胎されてコントの背景に、つまり“笑い”に転化していた。テレビを視聴できるような階層にとっては、もはや笑って忘れてよい過去になったのだ。
しかし「ハチのす町」の住民たちのように、高度経済成長を下支えした日雇い労働者たちにとっては、保険の加入など望むべくもなく、貧困=病苦はなおも重い現実だったはずだ。大介が勤める近代的な総合病院と「ハチのす町」の対比はその意味で実に象徴的で、いずれも同時代の日本の医療をめぐる一面の真実でありつつ、後者は社会において不可視化されつつあり、それに抗するかのようにちばの筆は、「ハチのす町」にとりわけ熱を込めているように見える。つのだの指摘はそのあたりも見抜いていたのかもしれない。
そしてこの対比――高度な医療体制の発展と、そこから取り残される人々という断絶は、「医療マンガ」の元祖たる手塚治虫『きりひと讃歌』にも見て取れる。貧困を「因襲」に置き換えた形だ。手塚の『ブラック・ジャック』ではさらに顕著で、金持ちから法外な治療費をふんだくる一方で、子供や貧しい患者の依頼はほんの“気持ち”で受けてみせるBJのふるまいは、「赤ひげ」から「ハチのす」へ連なる系譜上にある。
後に、ながやす巧が、その名もズバリ「Dr.クマひげ」と題して挑んだように、「医療」の外部――とりわけ「貧困」によるそれ――にどう向き合うかは、医療マンガの重要なテーマの一つとなっていく。社会保障制度の外部にある動物医療を厳しい現実を描いた夏緑・ちくやまきよし『獣医ドリトル』もその系譜に加えてよかろう。
30年ほども続く低成長と経済格差の拡大、セーフティネットの破却に余念のない新自由主義の跳梁により、貧困による病苦は再び深刻化している。そこに切り込む作品が今後現れてくるかどうか――それはもはや「医療マンガ」というより、『闇金ウシジマくん』(真鍋昌平)の領分かも知れないが――注目していきたい。
1 『文藝別冊 総特集 ちばてつや』(河出書房新社、2011年)所収「ちばてつや作品解説40 1956~2008」p217の指摘に拠る。
2 例えば本稿では、ちばてつや『ちばてつや漫画館』(メディアファクトリー、1997年)p52などを参照した。
3 中野晴行「核兵器の恐怖とマンガ」(復刻版『消え行く少女 前編』付録解説、小学館クリエイティブ、2009年)p4。
4 以下、この段落の概括はすべて、吉備能人「少女たちの夢のゆくえ――少女マンガの世界」(貸本マンガ史研究会 編・著『貸本マンガRETURNS』、ポプラ社、2006年)p154~160に基づく。