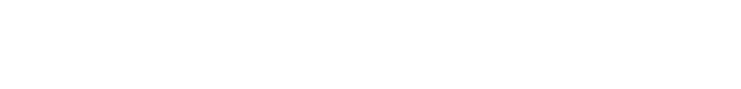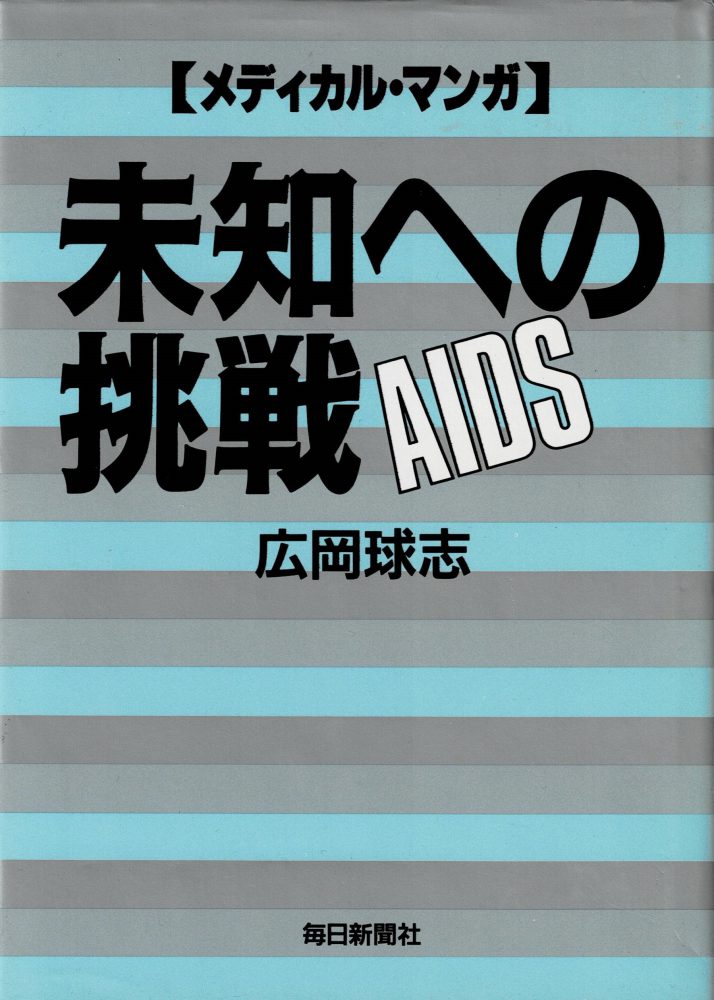サウザンコミックス編集主幹/フランス語翻訳家
原 正人
この度、サウザンコミックスの第2弾としてMK・サーウィック『テイキング・ターンズ―HIV/エイズケア371病棟の物語』(中垣恒太郎訳、サウザンブックス社)が出版された。作者のMK・サーウィックは、1990年代にアメリカ・シカゴのイリノイ・メソニック医療センター「371病棟」というHIV/エイズ専門病棟で看護師として働いていて、本書はその当時のことを回想したコミックスである。
HIV/エイズがマンガの中でどのように描かれてきたのか、ここで一度整理しておきたい。
HIV/エイズ
まずはHIV/エイズについて基本的な情報をおさらいしておこう。
エイズ(AIDS)とは、英語のAcquired immunodeficiency syndromeの略語で、日本語では後天性免疫不全症候群とも翻訳される。ヒト免疫不全ウイルスが人間の免疫細胞に感染し、それを破壊することで、後天的に免疫不全を起こす疾患で、このエイズの原因となるヒト免疫不全ウイルスを指す英語がHuman Immunodeficiency Virus、略してHIVである。HIV感染すなわちエイズというわけではなく、HIVに感染し、免疫機能が低下した結果、23ある合併症のいずれかを発症した状態をエイズと言う。
エイズの公式的な症例報告がアメリカで初めてなされたのが1981年のこと。当時はまだエイズという名称すらなく、翌1982年にエイズという命名がなされ、さらにその翌年の1983年になってようやくその原因がHIVウイルスであると特定された。
もっとも当時は、原因がわかったところでエイズを治療する有効な手立てはなく、エイズを発症することは死を意味し、実際多くのHIV陽性者が亡くなっている。アメリカ疾病予防管理センター(CDC)がインターネット上で公開している「HIVとエイズ―アメリカ合衆国、1981~2000年」 という記事によると、1981~1987年の6年間のHIV陽性者は50,280人で、その内47,993人が亡くなっている。1988~1992年の4年間には陽性者数202,520人、死者数181,212人と激増し、1993~1995年には、わずか2年間で陽性者数257,262人、死者数159,048人に及んでいる。もちろん抗HIV薬も作られていたが、その効き目は限定的なものだった。
そういった状況が変わるのが1990年代後半のこと。3種の抗HIV薬を併用するHAART(Highly active anti-retroviral therapy:高活性抵抗レトロウイルス療法)という多剤併用療法が確立されることで、死者数が激減する。1996~2000年には、HIV陽性者数は264,405人に対し、死者数は59,807人だった。
1990年代後半以降、とりわけ先進国において、エイズはかつてのような不治の病ではなくなったわけだが、全世界レベルで見れば、アフリカやアジア、ラテンアメリカなどを中心にまだ非常に多くの人たちがエイズとともに生きることを余儀なくされている。国連合同エイズ計画(UNAIDS)によれば 、2020年時点で全世界のHIV陽性者の数は約3,770万人、その内、抗HIV治療を受けている人は2,700万人、新規にHIV陽性者になった人の数は150万人、エイズで亡くなった人は68万人に及ぶ。1981年以降のHIV感染者累計は7,750万人、死者累計は3,470万人にもなるのだという。
HIV/エイズを取り上げたマンガ
1980年代から現代に至るまで、HIV/エイズは世界の大問題であり続けている。そう考えると、マンガの題材として取り上げられるのはごく自然なことだろう。実際、日本にも海外にも、HIV/エイズを描いたマンガはいろいろと存在している。
身近なところで日本のマンガでは、アメリカを舞台にゲイの主人公たちの純愛を描いた羅川真里茂の名作『ニューヨーク・ニューヨーク』(全4巻、白泉社、1998年)に、エイズで亡くなる登場人物が登場する。この作品は今も文庫版で気軽に読むことができるし、日本のマンガの中に描かれたHIV/エイズとしては、最もよく知られているものなのではないかと思う。
その他、どちらも『ニューヨーク・ニューヨーク』より前に発表された作品だが、秋里和国『TOMOI』(小学館、1987年)と永井明作、里見桂画『研修医古谷健一』(全4巻、秋田書店、1991~1992年)も、それぞれ異なった形でHIV/エイズを取り上げている。
このように作中の一要素としてHIV/エイズが描かれるケースは他にもたくさんあるのではないかと思う。海外でも事情は同じだろう。ユニークなものとしては、あいにく筆者は読んでいないが、アンドレ・タイマンス『カロリーヌ・ボールドウィン』(André Taymans, Caroline Baldwin, Casterman, 1996-)という現在18巻まで刊行されている探偵もののバンド・デシネ(フランス語圏のマンガ)があって、主人公の私立探偵カロリーヌ・ボールドウィンは、カナダの先住民ヒューロン族の血を引く母親とアメリカ人の父親の間に生まれた娘で、HIV陽性者という設定である。
当然、アメリカのコミックスにもHIV/エイズが一要素として使われている作品はある。スーパーヒーローのケースをふたつほど紹介すると、マーベルコミックスのキャラクターであるノーススターことジャン=ポール・ボービエはゲイであることをカミングアウトし、エイズに罹った赤ん坊を養子にしているし、DCコミックスのキャラクターである2代目スピーディことミア・ディアデンはHIV陽性者である。
HIV/エイズという悲劇
作品の一要素として用いるにとどまらず、HIV/エイズに正面から取り組んでいるマンガも、もちろん存在する。その最初の作品がなんであったのか、あいにく筆者は知らないが、1980年代後半には既にそういった作品がいくつか日本で出版されている。
その時期のマンガとして特に紹介しておきたいのが、広岡球志『未知への挑戦 AIDS』(毎日新聞社、1987年)である。
物語の舞台は本書の出版当時、エイズに対する不安が急激に高まりつつあった時代の日本。主人公の看護師・水沢ゆきと医師・織田吾郎が働く城西大学病院に、ある日、エイズ患者がかつぎこまれる。突然のことに病院側はパニックに陥るが、やがて院長の指示でエイズ研究室が設けられ、恋人同士のゆきと吾郎は、ともにそこで働くことになる。意義ある仕事に就き、私生活では婚約も交わし、順風満帆かと思われたふたりだが、輸血用血液の検査をしている最中に、誤ってゆきがそれをこぼし、HIVに感染してしまう。ゆきはたまたまペットのウサギに擦り傷を作られていて、そこからウイルスが侵入してしまったのだ。さらに悪いことに、ゆきは吾郎の子を身ごもっていた。結局、ゆきは出産を決意し、吾郎もゆきの決断を尊重する。
今読むと、HIV/エイズのさまざまな問題を詰め込めるだけ詰め込んだ都合のいいストーリー展開に、正直苦笑を禁じ得ない作品ではあるが、本書が刊行された時代を考えると、そのアクチュアリティは高く評価されていいのではないかと思う。日本人初のHIV陽性者が確認されたのが1985年。日本人女性初のHIV陽性者が確認されたのが1987年。まさに同時代のことなのだ。病院にかつぎこまれたエイズ患者は、輸入血液製剤でHIVに感染した血友病患者だが、その血友病患者の原告団が国と製薬会社5社を相手取り訴訟を起こすのは、本書刊行2年後の1989年である。
その血友病患者の悲劇に焦点を当てたのが、原作:広河隆一、漫画:三枝義浩『AIDS 少年はなぜ死んだか』(講談社、1993年)である。ちなみに本書には表題作の他に「危険な雨―ひろがるチェルノブイリ事故の被害」も収録されている。
血友病患者の中学生・渡辺明は、アメリカから輸入された血液製剤のおかげで、何不自由ない暮らしを送っている。ところが、自分と同じく血友病を患う先輩の吉田一郎が、その血液製剤が原因でHIVに感染したという衝撃の事実を知る。その後、一郎は運悪く交通事故にまきこまれる。救急車で搬送される際に、一郎は自分がエイズであることを告げるが、それが原因で受け入れ先の病院が見つからず、治療を受けることができずに亡くなってしまう。同じ血友病患者として一郎の事件に憤る明だが、やがて彼もまたHIVに感染していることが判明する。
物語の冒頭、原作の広河隆一が作画の三枝義浩に日米のエイズ患者の割合の違いをレクチャーするシーンがあるのだが、これが実に印象的である。アメリカではエイズ患者の約6割を男性同性愛者が、2割を薬物濫用者が占めているのに対し、日本では血友病患者だけで7割以上を占めているのだ。
本書は、「薬害エイズ」訴訟が行われている最中の1992年から1993年にかけて、『週刊少年マガジン』に掲載され、その後、単行本として出版された。反響のほどは定かではないが、大手週刊少年誌にこのような問題提起的な作品が掲載されたことが興味深い。なお、同じ作者コンビはその後、『AIDS 2 告げられなかった真実』(講談社、1996年)も出版している。
同じ時期に出版された作品をもうひとつ紹介しよう。山本利雄監修『まんがで読むエイズ』(善本社、1994年)である。本書は「エイズを知る」と「エイズを考える」の2章立てで、それぞれ「田口さん家の場合」と「北沢さん家の場合」というマンガが収録されている。タイトルから想像されるように、学習マンガ的な趣の作品で、この手の作品は1990年代に複数出版されている。
「田口さん家の場合」は、社員旅行でタイのバンコクを訪れた妻子ある中年男性の田口が現地で買春をし、日本に帰国してから、HIVに感染したのではないかと怯える様子を描く。「北沢さん家の場合」では、妊娠8週目を迎え、充実した夫婦生活を送っている北沢美智子が、同窓会でかつての恋人・藤本がエイズで亡くなったことを知る。不安になりHIV検査を受けたところ、陽性であることが判明。悲嘆にくれつつも、彼女は夫に事の顛末を伝える。
エイズが、医療従事者や血友病患者ではない、ごく普通のサラリーマンや主婦にも振りかかりうる災難として描かれているのが興味深い。
1980年代後半から90年代前半にかけて出版された、HIV/エイズをテーマにした3つの日本のマンガを紹介したが、それぞれ違いはあるにせよ、この3つはいずれも、平穏な日常を突然脅かす悲劇としてエイズを描いている。有効な治療法がまだ見つかっておらず、エイズが死に至る病であった時代のこと、それも当然と言えば当然なのだろう。
HIV/エイズとともに生きる
これらのエイズを描いた日本のマンガとは一線を画すバンド・デシネが、2001年、スイスで出版された。フレデリック・ペータース『青い薬』(原正人訳、青土社、2013年)である。1990年代以降、バンド・デシネでは自伝的作品が流行し、さまざまな傑作が生まれるのだが、『青い薬』もその文脈の中で生まれた作品である。
2000年1月1日、仲間内で行った年越しパーティーで、30代の作者は、かつて青春時代に片思いをしていた女性カティと再会する。カティは結婚し一児を儲けていたが、夫と離婚する決断を下したところだった。逢瀬を重ねていく内にふたりは恋に落ちる。ついに結ばれようというその晩、カティは作者に告白する。実は彼女も息子もHIVに感染していたのだ。作者の頭の中は一瞬真っ白になるが、そのことを受け入れ、彼はカティと彼女の息子と一緒に生きていく決心をする。
物語が描くのはふたりのHIV感染者と暮らす作者の日常であり、それに伴う遅疑逡巡である。作者の両親にHIV感染のことをどう伝えたらいいか、実の子ではない息子とどう接したらいいか、HIVに感染して(させて)しまったのではないか、セックスをする際には常にコンドームをしなければならないのか……。
陽性であることが発覚したカティの息子は、作中でHAART療法を受けている。エイズはここではもはや、1980年代から90年代前半にかけての日本のマンガに描かれていたような治療不可能な悲劇的な病ではない。適切な治療を受ければ、他の人とそう変わらない生活を送れる病であり、ともに生きていく病なのである。
『青い薬』は十数カ国語に翻訳され、HIV/エイズをテーマにした自伝的マンガの傑作として、国際的に高い評価を受けている。
『青い薬』出版から約15年、HIV/エイズをテーマにした新たな傑作として2017年にアメリカで出版されたのが、この度翻訳されたMK・サーウィック『テイキング・ターンズ―HIV/エイズケア371病棟の物語』である。
本書もまた作者の体験を綴った自伝的な作品だが、1990年代のアメリカでHIV/エイズ専門病棟の看護師として働き、今現在、グラフィック・メディスンという運動を推進するMK・サーウィックが描いた本書は、もっぱら愛する家族のことを綴った『青い薬』とは、おのずから異なる。
本書の魅力については、ぜひご自身でお確かめいただきたいが、本書がHAART療法でエイズ治療が劇的に変わる前後の現場の様子を描き、さらに十数年の歳月を隔ててその当時のことを振り返るという射程の長い貴重な記録であり、タイトルに示唆されている通り(テイキング・ターンズには「かわりばんこ」という意味がある)、医療は必ずしも一方通行ではなく、看る側はいつでも看られる側に変わりうるのだという発想を持った作品であることは強調しておきたい。作者のMK・サーウィックは、医療を包括的にとらえ、マンガを通じて患者と医療従事者をつなぐことを目指すグラフィック・メディスンという注目すべき運動の旗手として現在活躍中だが、本書に記されている通り、彼女をそこに導いたのは、HIV/エイズケア病棟での経験に他ならない。